子どもにスマホを持たせたいけれど、有害なサイトや使いすぎが心配…。
そんな悩みを持つ保護者の方に向けて、この記事では「フィルタリング機能」の基礎から、通信会社・OS別の活用法、親としてできる安全対策までをわかりやすく解説します。

2025年最新版の情報をもとに、安心してスマホデビューできる準備を一緒に進めましょう。
- フィルタリングで出来ること
- フィルタリングサービスの違い
- 親はどのようにサポートすべきか
子どもにスマホを持たせるときの基本知識
スマホを持つ年齢と保有率の現状
近年、子どもにスマートフォンを持たせる家庭が急増しています。
総務省の「令和6年度青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、小学6年生のスマホ所持率は約65%、中学生になると92%を超えています。
その背景には、連絡手段としての必要性や、学習アプリ・動画学習コンテンツの普及が挙げられます。
しかし便利である一方、リスクも無視できません。
子どもの年齢や発達段階を考慮しながら、スマホの利用を始める時期やルールをしっかり考える必要があります。
スマホに潜むリスクとその対策
スマホは便利なツールである一方、依存やSNSトラブル、有害なコンテンツへのアクセスといったリスクを伴います。
特に中高生は判断力が未成熟なため、知らない相手とのトラブルに巻き込まれるケースも報告されています。
このようなリスクに備えるために必要なのが「フィルタリング機能」の活用です。
機能を適切に設定すれば、アクセス制限・時間制限・アプリ制限などを通じて、安全な利用環境を整えられます。
フィルタリングでできることと活用のポイント
有害コンテンツからの保護
フィルタリング機能の第一の目的は、不適切なサイトやアプリから子どもを守ることです。
たとえば、アダルト系コンテンツや暴力的なサイト、詐欺ページなどへのアクセスを自動的にブロックすることができます。
これにより、子どもが誤って不適切な情報に触れてしまうリスクを大幅に減らすことができます。
また、App StoreやGoogle Playにある年齢制限付きのアプリも利用不可にできます。

親が知らないうちに、危険なアプリを使ってしまう心配も軽減されます。
利用時間やアプリの制限
フィルタリングサービスには、スマホの使用可能時間を細かく制限する機能もあります。
夜9時以降は自動的にロックする、1日あたりの利用時間を60分に制限する、といった設定が可能です。
さらに、YouTubeやSNSなど時間を奪いやすいアプリの使用時間を個別に管理することもできます。
これにより、学習時間や睡眠時間を確保しやすくなり、生活習慣の乱れを防ぐことができます。
位置情報共有による安心感
GoogleファミリーリンクやiPhoneの「探す」機能を使えば、子どもの現在地をリアルタイムで確認できます。
通学や習い事の帰りなど、遅い時間でも安心して見守ることが可能です。
また、特定エリアへの出入りを通知する「ジオフェンス機能」があるアプリも存在し、見守りをさらに強化できます。

これらの機能を活用することで、子供がスマホを安全に利用できる環境を作ることができますよね。
フィルタリングサービスの種類と選び方

通信会社が提供するサービスの特徴
| フィルタリングサービス | 通信会社 |
|---|---|
| あんしんフィルター | docomo au ソフトバンク ワイモバイル UQ povo LINEMO irumo |
| あんしんウェブフィルター | ahamo |
| あんしんコントロール | 楽天モバイル(330円/月) |
| iフィルター | mineo(385円/月) IIJ mio(396円/月) |
| セキュリティプラス | イオンモバイル(220円/月) |
NTTドコモ、au、ソフトバンクなどの大手キャリアは、それぞれ「あんしんフィルター」などのフィルタリングサービスを提供しています。
これらは月額無料の場合が多く、スマホ契約時に同時設定されることもあります。
特徴としては、操作がシンプルで、サポート体制が整っている点が挙げられます。
ただし、格安SIMを利用している場合は月額課金が発生することもあるため、注意が必要です。
OS標準機能を活用する方法
Android端末には「Googleファミリーリンク」、iPhoneには「スクリーンタイム」が標準で搭載されています。
これらは無料で利用可能であり、アプリごとの利用時間制限や、インストール制限など細かな設定ができます。
保護者のスマホと連携させれば、遠隔での管理も可能です。
操作に慣れている人にはこちらのほうが柔軟性があり、おすすめです。

下の記事で詳しく紹介しています

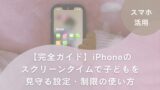
どちらを選ぶべきかの判断基準
操作の簡単さを重視するなら通信会社のサービスを、細かくカスタマイズしたい場合はOSの標準機能がおすすめです。
また、利用中のスマホがiPhoneかAndroidかによっても選択肢が異なります。
併用も可能なので、子どもの年齢や使い方に応じて最適な方法を組み合わせて使いましょう。

携帯会社に勤めていた時の体感ですが、あんしんフィルターは設定が簡単でした。
ファミリーリンクとスクリーンタイムは細かい設定ができて、不具合が少ないように思えます。
親ができるスマホサポートの工夫
定期的な設定見直しのすすめ
フィルタリング設定は、子どもの年齢や生活習慣に応じて定期的に見直すことが大切です。
たとえば、小学生のうちは厳しめに、中学生以降は少しずつ制限を緩めて自主性を育てる方向にシフトします。
時期ごとに「今の制限は適切か?」を見直すことで、スマホとの健全な距離感を保てます。
親子の対話を大切にする姿勢
一方的に制限をかけるだけでは、子どもは反発しがちです。
「なぜ制限が必要なのか」「どうしてこの設定にするのか」などを丁寧に説明し、子どもの理解と納得を得ることが重要です。
信頼関係を築いた上でのルール作りは、トラブル防止にもつながります。
家庭でのスマホルール作り
家庭内で「スマホの使い方ルール」を紙にまとめ、見えるところに貼っておくのも効果的です。
例えば、「夜9時以降は使わない」「食事中は持たない」など、具体的なルールを共有します。
このような明文化された約束は、家族全体の意識を高め、スマホの健全な使用習慣を促します。
子どもの未来を守るために、今できるスマホの使い方とは?
フィルタリングは、スマホを持たせるうえでの「安心のスタートライン」です。
ただ制限をかけるだけではなく、子どもと一緒に使い方を学ぶ姿勢こそが、デジタル時代を生きるうえでの大切な教育になります。
今回ご紹介したサービスや設定方法を活用すれば、家庭ごとに最適なスマホ環境が整えられるはずです。
親子で話し合いながら、安全で前向きなスマホ活用を始めていきましょう。
「見守る」と「任せる」のちょうどいいバランス、今から作っていきませんか?




コメント